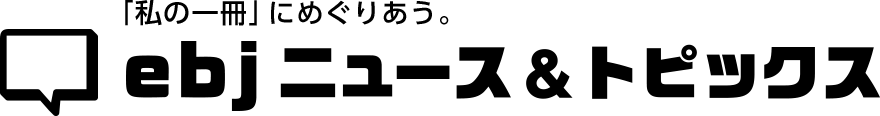【漫画家のまんなか。vol.18 新田たつお】「自分がなりたいヒーローを描いている」 デビューから50年、新田たつおが語るマンガの流儀

トップランナーのルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。
『静かなるドン』連載終了から10年余。現在、新シリーズ『「静かなるドン」―もうひとつの最終章―』を連載中のマンガ家・新田たつお先生にお話をうかがいます。
本格デビュー作となった『台所の鬼』の発表から、来年(2025年)で50年目を迎える新田先生。漫画家としての道のりと、これからの展望をお聞きしました。
▼新田たつお
1953年、大阪府生まれ。1970年、高校在学中に描いた『母と子の詩』で「週刊少年サンデー」新人まんが賞を受賞。奈良芸術短期大学卒業後、美術教員として大阪府内の中学校に勤務。1975年、『台所の鬼』が「週刊少年マガジン」新人漫画賞を受賞して本格デビュー。
上京して、『怪人アッカーマン』『ビッグ・マグナム黒岩先生』『こちら凡人組』などでヒットを飛ばす。代表作『静かなるドン』は、「週刊漫画サンデー」で1988年から2013年まで足掛け25年に渡って連載される人気作となった。
『静かなるドン』で、第42回日本漫画家協会賞大賞を受賞。2024年現在、「グランドジャンプ」で『「静かなるドン」―もうひとつの最終章―』を連載中。


「俺は第2の手塚治虫になる」と叫んだ小学生がいた
自分でマンガを描き始めたのは、小学校の5年か6年かの頃だったが、その頃から漫画家になると心に決めていたと思う。公園のジャングルジムのてっぺんで「オレは第2の手塚治虫になる」と叫んだこともある。その頃の子どもの誰もがそうだったように、自分も手塚治虫先生のマンガが大好きだった。だけど、誰もが“手塚治虫”になれるわけではない。多くの者が途中で挫折してしまうものだけど、自分は諦めることができなかっただけで、プロになった。
手塚先生のマンガで好きだったのは『鉄腕アトム』だとか、エンターテインメント性の強いもの。高尚なものより俗っぽいものが好きだった。それと大河ドラマが好きで、リス人間の少年・リッキーが活躍する『0マン』なんかも気に入って、夢中になって読んでいたね。
自分は短編マンガも描いているけど、どちらかというと大長編マンガの方が似合っていると思う。第一に、自分はスロースターター。連載を始めていきなり1位、2位になるなんてことは絶対にない。最初はドンケツでも、徐々に人気を上げていき、気づけばベスト3に入っている。それが自分のマンガのパターンだと思う。
子どもだから、まだ落書きみたいなものだったけど、小学生の頃から絵はたくさん描いていた。赤塚不二夫先生のマンガが好きだったので、おそ松くんやチビ太を真似したような絵を描いていた。他に好きだったのは、横山光輝先生の作品。『鉄人28号』には、ギルバートやブラックオックスといった、最強の敵役ロボットが現れる。それも続々登場するから、思わず何度も読み返したくなる――こんなマンガを描いてみたいと思ったし、今もその思いは変わらない。
手塚先生の『鉄腕アトム』も横山先生の『鉄人28号』も載っていたし、一峰大二先生の『電人アロー』も好きで、「少年」(光文社)は購読して読んでいた。組み立て付録も楽しみで、空母がついてきた時には嬉しかった。あの時代のマンガ誌には夢があったなぁ。
マンガで商売した中学生時代
自分が通っていた中学校はマンモス校。メシよりマンガが好きだったこともあって、読むだけでなくマンガを描くようになっていった。
SFが好きだったこともあって、小説もたくさん読んでいた。特に、挿絵画家の小松崎 茂さんが表紙や口絵を描いた「少年少女世界科学冒険全集」(講談社)シリーズなんかは、全巻を読むために学校図書館に通い詰めている。このシリーズには、ハインラインの名作『宇宙戦争』だとか、いろんなSF作品が収録されていたんだ。そんな縁で仲良くなった図書館の司書の先生に、小松左京さんが訪ねてくると聞かされた。当時の小松さんは、『日本アパッチ族』を書いてデビューした新進のSF作家だったけど、自分が描いていた『Zマン』というタイトルのマンガを見てもらったと思う。そこでマンガ雑誌「COM」(虫プロ商事)への投稿を勧められた。その後、中学3年の時から雑誌の投稿コーナー「ぐらこん」に投稿するようになって、本名の島田好晴の名で何回か載っている。
中学時代には、マンガで商売をして職員室に呼ばれたこともある。カーボン紙、複写紙の一種だけど、これでマンガを描いて複製し、級友たちに100円で売っていたのがバレたんだ。当時は謄写版(とうしゃばん)なんて印刷機(ガリ版といっていた)があったが、そんな高価なものは買えない。そこで安価なカーボン紙に目をつけたんだよね。
この1件で怒られもしたけど、かばって、褒めてくれた先生がいたのは嬉しかった。体育の先生に伝わって、怖そうな外見だったから「ヤバい!」と思ったけど、「カーボン紙なんかで描くな。謄写版を貸してやる」といわれた。「こんな大人もいるんだな」と感心したね。高校生になると、学級新聞の担当になった。そこでマンガを描いたら、クラスのみんなが喜んで読んでくれた。自分の作品は皮肉が効いていたから、高校生にも笑ってもらえたと思う。
マンガ新人賞に入選するも、大学に進学
本格的にペンを入れ始めたのは、高校1年生の頃。2年生になって投稿したマンガ『母と子の詩』が、「週刊少年サンデー」(小学館)の新人まんが賞に2席で入選した。
僕は高校1年で結核にかかって、入退院を繰り返している。あれで人生観が変わって、「マンガを本格的に描いてみようかな」と思わされたんだ。入院中に母が買ってくれた「週刊少年サンデー」で、ジョージ秋山先生の『銭ゲバ』に衝撃を受けた。その影響が、入選作や初期作品に色濃く出ている。
この時に3席に入ったのが、柳沢きみおさんだったと思う。彼が21歳で、自分は16歳。彼も若かったが、自分はさらに若い。「週刊少年サンデー」の本誌に連載したものの、実力不足であるのが明白だった。東京へ出ていく自信がなくて、絵の基礎から学び直さなければと思って、奈良芸術短期大学に進学。そこで石膏デッサンに打ち込んだのも、今となってはいい思い出だね。
教師生活をマンガに生かす
短大を卒業したものの、マンガを描いてもすぐ食えるとも思えない。親父が商売に失敗したこともあって、家にはほとんど金がない状態。そこで、美術の教員採用試験を受けて、大阪の河内地方のとある中学校で教えることになった。時代は、ちょうど校内暴力の嵐が吹き荒れていたあたり。美術の授業なんて、真面目に受けるヤツはほとんどいなかった。
これは才能というのか分からないけど、「これはマンガに使えるな」と思った人間は、よく覚えている。だから、学校の先生になった経験も無駄じゃなかったと思う。生徒はもちろんだけど、同僚の先生たちの様子もよく見ていた。熱血の先生に限って、生徒から殴られたりする。生真面目に、ツッパリに忠告したりするからね。教員時代に学んだ“悲哀”みたいなものは、のちのマンガ作品に生かせたと思っている。
非常勤講師は時間で雇われているわけで、比較的に自由に勤務できる。3時限から授業があれば、それなりの時間に学校に行けるわけ。生徒たちからは、先生が遅刻したとはやし立てられたけど、別に遅刻というわけではない。こうして自由な時間が持てるようになり再びマンガを描き始めた。
再デビュー作『台所の鬼』と、ペンネームの由来
なんとか1本描き上げたものの自信が持てない。その上、本名の島田好晴で応募して、それが校長にバレたら大変なことになると思った。そこで、短大時代のマンガ仲間だった新田辰雄君に頼んで名前を拝借。彼に原稿を預けて、「少年マガジン」の新人漫画賞に投稿してもらった。
それが入選した『台所の鬼』だけど、新田君は原稿を見せたところで「入選すると思っていた」と言ってくれた。新田君には、奈良駅前でステーキをご馳走して、自分のペンネームとして“新田たつお”の名前を譲り受けた。
これが、1975年に「月刊少年マガジン」(講談社)に掲載されて再デビューしたわけだけど、このマンガは親父がモデル。自分の父親は商売していたものの、倒産騒ぎに巻き込まれて全てを失っていた。絶望からか2年間一言も喋らなかったけど、ただ一つ興味を持ったのが台所だった。いつも何かしら漁(あさ)って食べていた。人間は人生に失望すると食べることしか興味がなくなるのかと思ったら、マンガが1本描けた。それが『台所の鬼』になっている。

青年コミック誌に活路を見い出す
『ガクエン遊び人』(「週刊少年マガジン」掲載)で、消火器を持って暴れ回る主人公を描いた。舞台にしたのが、自分が教員として働いていた中学校。それがバレてしまって、定年間近の校長に泣きつかれて辞表を出している。
「少年マガジン」編集部から、東京へ出てこないかと誘われた。中学校を退職していたこともあってすぐに上京したけど、その時の所持金は20万円。教師をやって貯めていた全額だった。東京に着いてアパートを借りたけど、1ヶ月の賃料は2万2千円。練馬区の保谷だったけど、講談社のある護国寺に行くのにも便が良かった。作品を認められたのか、「少年マガジン」の専属となり、作品を見せに編集部に通わなければならなかったからだ。専属料は1ヶ月5万円。そこから家賃を引くと大して残らない。
その頃の思い出といえば、アパートの下の階の住人が流す音楽がうるさかったこと。とにかく大音量で、マンガの執筆に集中できないんだ。思わず床をドンドン叩いたら、相手が怒鳴り込んできた。ドアを開けたら強面(こわもて)の男性が立っていたので、即座に謝ったけどね。それだけじゃ足りないと思って、菓子折りを持って後日もう一度謝りにいった。そうしたら、以降その男性がすごくいい人になって挨拶もしてくれるようになってね。世界平和の秘訣はこれ、すぐに謝ったらいいんだよ(笑)。
お金のため、1本でも多くマンガを描かなければ……と編集部にネームを運ぶが、これが実にきつい。「編集会議にかけたがダメだった」という答えが返ってくる。さすがに編集長が、ボツになった分の原稿料を払うと言ってくれたが、自分の方から断った。その代わりに、「少年誌とバッティングしない青年誌だったら、他所で描いても良い」と言ってもらった。ちょうど双葉社から依頼があって、「コミックギャング」という雑誌を創刊したから「描いてください」という。それで描いたのが『怪人アッカーマン』。
「コミックギャング」には、どおくまんさんも描いていた。他にも、能條純一さんや谷口ジローさんのような才能の持ち主が、綺羅星のごとく出ていったんだ。いまや伝説の雑誌だけど、自分が描いた下世話で破壊的なSFパロディも、受け入れられて人気になった。この成功の後、少年誌で描くことはなくなり、青年コミック誌が自分の活動の場となっている。


『静かなるドン』誕生までの道のり
次のヒット作となったのが、『ビッグ・マグナム黒岩先生』(双葉社「別冊漫画アクション」掲載)だ。この作品の主人公・黒岩先生は、不良生徒相手にマグナムをぶっ放すバイオレンスな先生。映画化もされた作品だけど、「教師時代の経験を生かしているのでは」とよく聞かれた。しかし、自分は弱いし、第一ケンカをしたこともない。中学で美術を教えていた時も、生徒たちへの生活指導をやる必要はないと思っていたし、実際にやっていない。自分は正義漢ぶって人にあれこれ言うのが嫌いだったからだ。
殴るアクションなんかも、全部想像で描いている。『静かなるドン』みたいな極道マンガもそうだけど、“自分にないもの”を描いている。“自分がなりたいヒーロー”を描いているんだね。そこに、読者が共感してくれるんだと思う。
「平凡パンチ」(マガジンハウス)に連載した『こちら凡人組』も人気となった。その人気に注目したのか「週刊漫画サンデー」(実業之日本社)編集部から「『こちら凡人組』の続きを描かないか」と言われた。それまでに「週刊漫画サンデー」ではいくつかのナンセンスギャグの連載をしていたが、『こちら凡人組』ほどのヒットにはなっていなかったので、自分でも続きを描きたいと思った。ところが「平凡パンチ」から、「他誌で続編を描くのはダメだ」と言われてしまったんだ。それで言わば仕方なく捻り出したのが『静かなるドン』だったわけ。そんな始まりだったが、描いてみたらどんどん乗ってきて人気も出た。2年くらいしたら「平凡パンチ」が休刊してしまい、『静かなるドン』と平行して『こちら凡人組』の続編『となりの凡人組』『それからの凡人組』まで描くことになった。週刊連載2本なんて、我ながらよくやったよ。


ギネス記録級の長編になった理由
『静かなるドン』は、最初の考えでは3年ほどで終わるつもりだった。それがコミックス108巻の大長編になったのは「週刊漫画サンデー」編集部の強い要望があったから。雑誌の稼ぎ頭だから、連載が終了したら困るといってくれたのだ。本当なのかとも思ったが、そこまで言われれば男子の本懐だ。
主人公の近藤静也は、ヤクザの3代目総長の顔と、下着会社プリティの平社員の顔と二つの顔を持っている。彼が思いを寄せるデザイン部の先輩の秋野明美。自分の最初のアイディアでは、明美が静也の正体を知ったところでエンドにしようと考えていた。静也と明美の恋の行方は……というところで、余韻を残しての終わり方だ。
それが、単行本も10巻、30巻、50巻、70巻と続いて、108巻で完結している。“108”という数字には意味がある。仏教では、人間の煩悩は108種類あるといわれているから、この数に合わせて締めくくりにしたいと思った。ここまで頑張れたのには、長年読んでくれているファンの存在があった。年配のファンから、きちんと完結させてほしいという応援の声をいただいたのも後押ししてくれたと思う。
本来の自分は、一つ所にいると飽きてしまう性格だ。それが25年も描き続けられたのは好きに描かせてもらったからだ。細かいことまで言われると萎縮してしまい、決して面白いものは描けない。原作もつかず、アイディア・ブレーンもいないで、よくも108巻も描き続けられたと、我ながら感心する。大人向けのマンガではギネス級のマンガではないかと思う。

『静かなるドン』🄫新田たつお/実業之日本社
近藤静也のキャラクター作りについて
矛盾する話に聞こえるかもしれないが、連載は長く続ける方が“楽”に決まっている。毎回新しいシチュエーション、キャラクターを考えるのはしんどいもので、同じパターンを使った方が楽という意味だ。だからといって25年もの連載だから、苦労はそれなりにあった。
主人公の近藤静也の魅力が、長期連載をけん引してくれた。「どのようにキャラクターを考えるのか」と人から問われることがあるが、自分の場合は戦略的にキャラクターを考えたりするタイプではない。“キャラクターは天から降りてくる”と思っている。ヤクザの3代目総長と、下着メーカーの平社員の二つの顔を持つ近藤静也のキャラにしても、打ち合わせと称して遊んでいたパチンコの最中に浮かんできたものだ。
近藤静也は新鮮組の3代目総長。幕末に活躍した新選組を下敷きにしている。そのせいか、女性のファンも大勢いたようだ。何より嬉しかったのは、自分が子どもの頃から大ファンだった赤塚不二夫先生との縁ができたこと。赤塚夫人が『静かなるドン』の大ファンだというのだ。それで食事に誘っていただき、入院された病院にお見舞いにも行った。そのお二人は今いらっしゃらない。御冥福をお祈りする。
マンガ創作を再開した経緯
“静かなるドン”こと近藤静也というキャラクターを動かすには、強いキャラクターを作るしかない。僕の物語の作り方は、バトルがメイン。戦っているシーンを描くのは疲れるし、嫌だと思うときもあるが、派手なバトルが人気の秘訣だと思う。
それも、ただのバトルではない。光と闇との戦いだ。近藤静也のバトルは、ヤクザ同士の抗争から、世界を牛耳る巨悪との戦いに広がっていく。そんな彼を支える秋野明美とのラブロマンスもあって、男性読者はもちろん、女性からも多くの支持を得ている。『静かなるドン』の根底には、愛の物語があるんだ。
だけど25年もバトルを描き続けたら、さすがに疲れた。『静かなるドン』を描き終えたら、しばらく休もうと決意していた。またマンガが描きたいという衝動が起きるまで待とうと考えた。
そして、その時がやって来る。2014年、「ビッグコミック」(小学館)に自衛隊物の『隊務スリップ』を描いた。さらに、「アサヒ芸能」に『凡人組VS.怪人アッカーマン』、『還暦アッカーマン』と続けて描いた。そして、ある洋館をきっかけに『静かなるドン』を再び描くことになる。
山下和美さんが進めていた洋館・旧尾崎テオドラ邸保存運動。妻の笹生那実が、この活動に参加していたことから、自分も協力することになった。それをマンガに描いた『世田谷イチ古い洋館に来た静かなるドン』を掲載した縁で、今は「グランドジャンプ」(集英社)に『静かなるドン―もうひとつの最終章―』を連載している。

読者が喜んでくれるマンガを描きたい
自分の原動力は、読者が喜んでくれること。例えば料理店なんかでも、お客さんに「おいしい」と喜んでもらうために、料理を作っているのだと思う。
コロナ禍の時には、外出せずに自宅で読める電子書籍がブームになったけど、ものすごい数のユーザーが『静かなるドン』の電子版を支持してくれた。連載が終わって10年近く経っていたのに、読者はドンの活躍を楽しんでくれた。それも連載時に読んでいた人だけではなくて、新しい読者もいるという。ファンが喜んでくれるなら、また『静かなるドン』を描かなければいけないと思った。
僕も、ついに70歳になった。いかに人を喜ばせるか──この年齢になって、今はそれしか考えていない。新シリーズは隔週誌の連載だけど、読者の喜ぶ顔を想像したら休めない。今日もこれから熱海の仕事場にネームを入れに出かけるよ。
取材・文・写真=メモリーバンク *文中一部敬称略