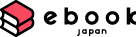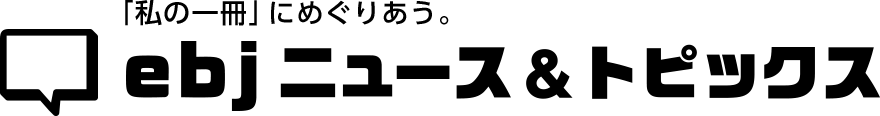【編集者のまんなか。vol.1 林士平】作家が生んだ漫画の世界をさらに広げるため、全方位で仕掛けていく

人気漫画家のルーツと今に迫る「漫画家のまんなか。」シリーズ。
今回は漫画家と二人三脚で作品を作る編集者にスポットをあてた番外編として、「少年ジャンプ+」の編集者・林士平(りん しへい)さんにお話を伺います。
『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』など数々のヒット漫画を手掛ける林さんが、子どもの頃に夢中になった漫画、編集者として駆け出し時代に出会った漫画界の巨匠たち、そして紙の漫画雑誌からアプリへと変わっていく時代のなかで、いかにしてヒット作を世に出してきたのか──。今注目している作品や今後のビジネス展開についてもお話を聞きました。
▼林士平
1982年生まれ。東京都出身。2006年に集英社入社。
入社後「月刊少年ジャンプ」に配属され、編集者としてのキャリアをスタート。入社2年目に「ジャンプSQ.」に異動し、雑誌の創刊に携わる。
2018年から漫画雑誌アプリ「少年ジャンプ+」編集部スタッフ。
『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』『ダンダダン』など、数々のヒット作品を手掛けるほか、アニメ・舞台・イベントの監修やプロデュース、アプリ開発など多岐にわたって活躍中。過去立ち上げ作品として、『青の祓魔師』『ファイアパンチ』『左ききのエレン』『地獄楽』『ルックバック』などがある。


漫画や小説に夢中になっていた少年時代
子どもの頃から漫画はよく読んでいました。「コロコロコミック」と「コミックボンボン」は親に買ってもらっていて、姉がいたので「りぼん」も毎月読んでいましたね。漫画は結構身近にあったと思います。
ただ父親が台湾人なんですが、漫画を買うことに関してあまり良い思いをもっておらず「図書館をちゃんと利用しろ」と言われていたので、最初は図書館にある『はだしのゲン』とか手塚治虫先生の漫画なんかを全部読みました。それでも読み足りなくてお小遣いで買ったり、漫画をいっぱい持っている友達の家に行って読んだりも。『こちら葛飾区亀有公園前派出所』はその友達の家で全巻読破しました。
1982年生まれなので『DRAGON BALL』『SLAM DUNK』『バガボンド』などもリアルタイムで読んでいる世代です。そのほか単行本で買っていたのは『幽☆遊☆白書』『俺たちのフィールド』『シュート!』『MAJOR』『まじかる☆タルるートくん』『YAIBA』など、ジャンルにはこだわらず話題になった漫画は何でも読んでいました。『寄生獣』は中学1年生の時に最終巻を書店に予約しに行ったことを覚えていて、初めて予約して買った漫画だと思います。表紙の絵がちょっとエグくて、幼い子どもが読んでいいのかな、と個人的に思っていたのでブックカバーをつけて読んでいましたね(笑)。
この頃の漫画は繰り返し読んでいるので、ストーリーはしっかり頭の中に入っています。とくに「コロコロコミック」は2日くらいで読んでしまって、読み終わってから次の号が出るまで繰り返し読みました。大人になって思いますが、親に禁止されているものほど子どもってハマるんですよね。この頃に読んだ漫画は大人になってから読む漫画とは回数が違います。
漫画雑誌を買い始めたのは中学生の頃から。「週刊少年ジャンプ」「週刊少年サンデー」「週刊少年マガジン」など、それぞれクラスのみんなで持ちよって回し読みしていました。実はそのときのクラスメイトが今「週刊少年ジャンプ」の副編集長をやっています。すごいですよね。めちゃめちゃ漫画を読んでいる人が集まっている不思議なクラスでした。
漫画に限らず映画や小説も好きで、とくに父親が映画好きだったので、録画した金曜ロードショーの映画を一緒に観ていた記憶があります。古本屋めぐりもよくしていましたし、小説では宗田理先生の「ぼくら」シリーズ、那須正幹先生の児童文学シリーズ「ズッコケ三人組」なども読んでいました。その頃は漫画家や出版社というものはあまり意識していなくて、純粋に漫画や物語の世界に夢中になっていたごく普通の少年だったと思います。
自由かつ実力主義の編集部。新たな才能を探しに全国各地へ
実は大学4年生になるまで編集者になることは考えていませんでした。いろいろな企業の採用試験を受けるなかで出版社も受けておくかという感じで受けたのが集英社で、せっかくなら漫画が一番売れている会社にしようと。とりあえず社会科見学で行ってみようという感覚ですね。
最終的に集英社に入社したのは給料がよかったからです。父親があまり就職することを良しとせず「自分でビジネスを立ち上げろ」という考えの人だったので、自分自身も3年くらいで会社員を辞めることを考えていました。だから入社3年目までに一番高い給料をもらえる会社に行こうと(笑)。自分でも現金で可愛げのない学生だったと思います。
正直、会社に入って自分がどんな仕事をするのかわからなかったという理由もあります。配属される部署によって仕事はだいぶ変わりますし、総務や経理に配属されたら想定と全然違う仕事をすることになる。一番保証されるのが給料だったので、その点を指針にして決めました。
でも実際に入社してみて集英社はすごく楽しい会社でした。「ジャンプ」グループにおいては競争原理が強い組織だなと感じる部分もありましたが、みんな優しかったですし勤務時間もフレックス。まだ当時は夕方に出社して朝まで働くおじさま方がいっぱいいましたし、そしてやたら毎日飲むんですよ(笑)。普通に朝5時とかに「築地に寿司食いにいくぞー」と言ってくる先輩もいて、内心「あと3時間で出社時間なんだけどな」と思いながら、一緒に食べに行っていた記憶がありますね。締め切りまでに仕事をして新企画をまわしていればOKというのが編集部のスタンスだったので、その自由な風土が自分には合っていました。

その後「ジャンプSQ.」に異動して雑誌の創刊メンバーになったのですが、創刊に立ち会えることってなかなかないので、お祭りみたいな感じで楽しかったですね。ちょうど時代の境目で、ありとあらゆるものをデジタル化していこうということで、入稿作業などは楽になったなという記憶があります。例えばネーム指定(セリフ部分の書体や文字の大きさの指定)なども、僕が入社した時はまだ吹き出しに手作業でシール貼っていたのですごく大変で。自分がシールを曲げて貼ったら、曲がって出版されてしまうんです。それがデジタル化されて時間に余裕ができたので、作家さんとの打合せに時間が取れるようになりました。
忙しかったですが、「大変な仕事は外の力を借りていいよ」という上司で、外部のライターさんやデザイナーさん、カメラマンさんに頼って一緒に仕事を進めることも多くありました。「苦労することが成果につながるわけじゃない」という考え方の部署だったので、それが良かったですね。
出張も好きにさせてくれていたので、地方の専門学校や美術大学・芸術大学に行きまくって、いろいろな作家に会いました。そこで学校の先生とも仲良くなるので、今でも「今度卒業生の作品展があるので来ませんか?」と案内をいただくことがあり、若い作家に会い続けられる関係性ができたことはすごく良かったと思います。
雑誌の数が少なくて作家さんの数が多い時代は、編集部に座っていれば作家さんが来るという状態がありました。担当が決まるのも運による部分が大きくて、「編集部にかかってきた電話を取った」「その月の担当だった」という理由のみで一緒に仕事する作家さんが決まることも。僕の場合は自分で探しに行くことも自由で、SNSで直接連絡をくれる方もいます。作家さんとの出会い方は大きく変わりましたね。
続々とヒット作が生まれる土壌となった漫画アプリ「少年ジャンプ+」
「ジャンプSQ.」には10年ほど在籍していたと思いますが、発行部数は削られ続けるというのを経験しました。コミックスの売り上げが伸びているタイトルやアニメ化されるタイトルがあったので売り上げとしては順調なんですが、部数的には結構しんどいなというのがずっと続いていた時期です。
ちょうどその頃に「少年ジャンプ+」の前身となるデジタル漫画アプリ「ジャンプLIVE」が始まりました。スタートしたばかりの新しいメディアだから他の編集部にも掲載協力依頼が来て、そこから「ジャンプSQ.」に在籍しながら、「少年ジャンプ+」で賀来ゆうじ先生の『地獄楽』や藤本タツキ先生の『ファイアパンチ』の連載をスタートしていった感じですね。
紙の雑誌はどうしてもページ数に上限があるので、年間で始められる連載本数は月刊誌でせいぜい4~6本ぐらい。編集部員が7、8人いると、等分で割って1人1本しか連載が始まらないのが現実です。僕はもっともっと始めたい作品があったので、上限がない「少年ジャンプ+」に異動願いを上司に伝えて、正式に異動となりました。


やっぱり自分が面白いと思った作品を立ち上げていく方が、性分に合っているんですよね。もちろんすべての作品が上手くいくわけではないので、作家さんとの関係性次第ではありますが、「上手くいかなかったらさっさと畳もう」ということも最初からお伝えしています。それでも『ファイアパンチ』や『地獄楽』、それから龍幸伸先生の『ダンダダン』も「ジャンプSQ.」では通らなかった企画・作家でしたけど、ちゃんと「少年ジャンプ+」でヒットして、今や大きな柱となるコンテンツです。そういう意味ではすごくハッピーだったなと思います。

編集者駆け出し時代に出会った、天才作家たち
今まで多くの作家の方と一緒に仕事をさせてもらってきましたが、本当に個性的な先生がたくさんいらっしゃいます。とくに駆け出し時代に出会った先生の印象は強く残っていて、柴田亜美先生は強烈な印象があります。今もたまにテレビで拝見しますが、相変わらずエネルギーの塊のような素晴らしい方だと思いますね。
稲田浩司先生と三条陸先生には1年目の頃に、編集者としてすごく伸ばしていただきました。『DRAGON QUEST‐ダイの大冒険‐』は子どもの頃に死ぬほど繰り返し読んだ作品なので、自分の中でお二人は憧れの存在。打ち合わせしている時は不思議な感覚でした。
稲田先生と三条先生との3人での打合せでは、稲田先生が作画するうえでの疑問点を大量に投げかけて、それに対して三条先生も無限のアイデアが湧いてきて、天才同士のキャッチボールで作品が磨かれていくさまを目の前で見ることができました。稲田先生の指摘される点は絵的にとても正しいというか、それを気にしないと確かに良い絵にならないよなと納得する部分が多くて、めちゃくちゃ勉強になりましたね。

秋本治先生とは『Mr.Clice』という作品でご一緒させていただいたんですが、これほどまでに資料を集めて物語を丁寧に構築している大ベテランの方でも、若造の僕の意見で目の前でネームを直すのかと驚いたことを覚えています。逆に怖くなる感覚もありましたね。さっき打合せでOKを出したネームでも、僕が編集部に戻ったらまたアップデートされたネームが届くこともあって。飽くなき探究心でもっと面白いと思うものに変えていく、そのフレキシブルさはすごいと思いましたし、それをめちゃくちゃ楽しそうにやられているんですよね。その姿勢を見習わねばというか、お仕事をご一緒できて本当にありがたかったです。

面白いと思う感覚を常にアップデートしていく
作家さんと向き合う際のスタンスは、1年目の頃に上司に言われた「彼女だったらどう対応するかを行動指針にしろ」という言葉が大きく影響していると思います。今はそこからもう少し広がって「家族だったらどうするか」という視点ですね。作家さんが迷ったり困って悩んでいたら、とりあえず会いに行く。もちろん相手によって距離感をちゃんと変えなきゃいけないですし、ビジネスパートナーとして礼を尽くすことが大前提ですが、そのうえで親戚や家族のような距離感で考えるバランスを大切にしています。
編集者として、まずは漫画として面白いものを作るのが第一で、日々そればかり考えています。感覚的には一読者のつもりの視点と編集者の視点の両方があります。面白さを追求するうえで、感覚的な意味で老いないことは意識していますね。新しいものにちゃんと触れ続け、それを楽しもうとすることが大事だと思います。新人作家さんに「何読んでる?」「何が最近面白い?」と聞いて、そこであがった作品はすぐさま読んで、次に会ったら「僕はこう思います」と感想を伝えています。頭ごなしに若い人が楽しんでいるものを否定しないとか、逆に若い子たちが何を楽しんでいるのかちゃんと見ようと思ってやっていますね。
ここ最近で面白いと思う作品はいろいろありますけど、例えば小説『成瀬は天下を取りにいく』は、キャラのいじり方が面白いなと思いますね。『スナックバス江』はアニメ化されると聞いて、どんなアニメになるんだろうと気になっています。『隣のお姉さんが好き』も好きですね。キャラがかわいいなって思いますし、『イリオス』も面白いなと思って読んでいます。芥川賞候補の作品も気になっていて、作詞家の児玉雨子さんが書いた『##NAME##(ネーム)』は読まなきゃって思っています。話題作はだいたい読んでいますし、気になる作品の情報に触れたらその瞬間にネットで買ってしまいます。読んでいないものがあったら、それは多分買ってあると思います。片っ端から買うことになるので、なかなか読み終わらないですね(笑)。

『地元最高!』とか『「子供を殺してください」という親たち』など、表現としてギリギリを攻めていて衝撃的だなと思いますが、僕は読んですごく面白かったので、こういう作品が世に出てくるっていい時代だなと思います。昔よりも表現の幅がだいぶ広がっている印象はありますし、同時に作品数も増えていると感じます。ここ数年の作品数はちょっと常軌を逸しているんじゃないかと思うくらい。でもあまり出版社がゲートキーパーをやりすぎるのも良くないと思っていて、もう漫画ってどこからでも出てくるじゃないですか。個人のホームページからも出てくるし、SNSからも出てくる。作品が面白いと評価されるかどうかは出してみないとわからないので、新しい作品が出やすい土壌というのは、豊かな土壌だと思っています。

言語や文化の壁、絵を描くことの壁を全部壊したら面白くなる
編集者としての仕事のほかに、アプリ開発なども行っています。漫画のネームを作れるアプリサービス「World Maker β版」を以前リリースしましたが、現在開発を進めているアプリは、漫画に限らず、アニメ、映画、CMなどの絵コンテも作れるサービスに拡大しています(※「World Maker」公式サイト)。「絵を描く」ということが障壁になっている人は世界中にたくさんいると思うので、絵が描けない人もネームが切れるようになったら、だいぶ人生が変わるんじゃないかなと思っています。同時翻訳機能も入れているので、日本語で書いた日記がアメリカでバズったり、ブラジルの少年が書いたサッカー日記がフランスのCMで使われたりしたら面白いなっていう。このアプリが世に出たらどんなふうに変わるかなっていう思考実験ですね。
日本の人口って確実に減っていくじゃないですか。日本の人口が減るのであれば、日本人だけに向けてエンタメを作っていると確実に売り上げが減るんですよね。一方で世界の人口は増えているし、世界にはまだ日本で作った作品が届いてないエリアが山ほどある。世界に対して作品を出していくという方が今後伸びていく可能性が高いので、世界を向いてやっていこうと考えています。
漫画の楽しみ方は、もっと広がっていく
今後やってみたいことはまだまだたくさんあって、とくにデジタルアートのイベントはどんどんやっていきたいなと思っています。去年のジャンプフェスタで『マンガダイブ』という展示を行っていて、その企画監修も経験させて頂きました。漫画から横展開して、漫画の世界やキャラクターを体感できるデジタルアートのイベントができたら、連載やアニメだけでなく、もっと違う軸でお客さんが楽しんでくれるかなと思っています。
もちろん原画展やテーマパークとのコラボレーション、2.5次元ミュージカルなどは今後もさらにやっていきたいですし、作家が生み出した漫画の世界をどう広げていくのか、思いつく限り全方位でやってみたいと思っています。
取材・文=白石さやか
写真=大沼博