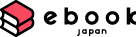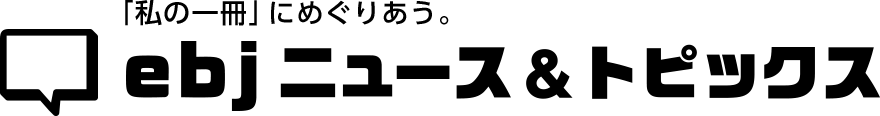『扇島歳時記』フィクションとノンフィクションで作られる物語の深みと”生命力”
高浜寛先生が描く『扇島歳時記』は、「月刊コミック乱」にて連載中の作品です。第24回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」を受賞した本作は、舞台となる長崎での膨大な調査を元に作成されています。今回は、実際の歴史や文化を題材に生まれた本作の魅力をご紹介。
異国文化満ちる出島で生きる少女
長崎の丸山遊郭で生まれたたまをは、姉女郎・咲ノ介の禿(かむろ)として、身の回りの世話をするため出島のオランダ人の邸宅に入ります。欧州の異文化が持ち込まれるこの小さな島で、異国人を含む彼女に良くしてくれる人々との豊かな交流が描かれているのが本作です。

『扇島歳時記』/高浜寛/1巻/第2話
開かれていく時代の流れとは裏腹に、抗うことのできないたまをの女郎になるべく宿命。そんな14歳の彼女の出島での”日常”が映し出されています。
遠く離れた時代にも存在する共通点
民族や身分の違う多様な人々が登場する本作には、彼らの”違い”を越えた心温まるエピソードが散りばめられています。
慣れない土地にも関わらず、カタコトの日本語で一生懸命コミュニケーションを図ろうと日本人に歩み寄る西洋人や、平民にも心優しく接しようとする侍の者。

『扇島歳時記』/高浜寛/1巻/第8話
彼らのあり方は、時代や視点が異なるだけで、LGBTやフェミニズムといったマイノリティや差別問題に向き合う現代の私たちと、何ら変わらないようにも見て取れるのです。
民族や身分など表面的なことにとらわれず、相手を丸ごと受け入れ想いやるからこそ可能な彼らのような関係性は、出島というごく小さな地区の中で紡がれ、彩られていきます。それは、たまをも例外ではありません。
非共感によって生まれる感情
たまをは、出島で出会う西洋人や日本人が大好き。彼らも同じように、無邪気で素直なたまをのことを大切に思っています。特に、出島で医師として働くトーン先生。幼少期の頃からたまを知っており、かわいがってくれていたオランダ人です。

『扇島歳時記』/高浜寛/1巻/第2話
親切にしてくれる人たちに囲まれながらも、たまをを待ち受けるのは女郎になる定め。それが、廓で生まれた彼女の人生です。西洋の文化や思想が持ち込まれ、人や文化が開かれていく中、たまをは自らの宿命と共に置き去りに。憂うべき運命とは似つかない彼女の朗らかな性格は、読者の心をより深くえぐっていきます...。

『扇島歳時記』/高浜寛/1巻/第2話
さまざまな物語に触れるとき、自分たちと似た境遇や体験によって強い共感が芽生え、心が動かされることは誰にでもあるはずです。けれど、たまをの物語はむしろ逆。私たちは彼女の経験や心情を、決して分かち合うことができない。彼女に歩み寄ることすらできない、密かに抱く痛みや悲しみをほんの少しでも背負わせてはもらえない不甲斐なさに胸が締め付けられてしまうのです。

『扇島歳時記』/高浜寛/1巻/第4話
もしたまをが現代に生まれていたならば、学校で学問を学び、友人たちと楽しく過ごし、そして帰る先には家族が待っていたはず。わずか14歳のたまをは、私たちの当たり前すら享受できないのですから。
事実ベースに描かれる物語の生命力
今を生きる私たちと何ら変わらない人と人との豊かな繋がり。一方で、今の私たちには決して体験することのできない経験や感情。この対極にある共感と非共感が混ざり合う『扇島歳時記』は、現地での取材や文献調査を重ねた高浜寛先生の努力によって生み出されています。フィクションやノンフィクションとも違う、一種の”生命力”を感じることができるのがこの物語。かつて出島に生きた人々に、自然と思いを馳せてしまう力があるのです。