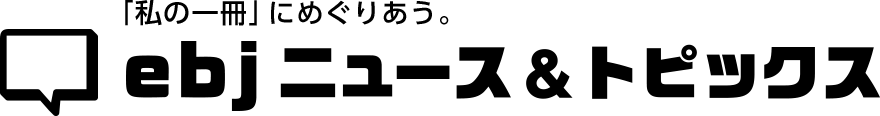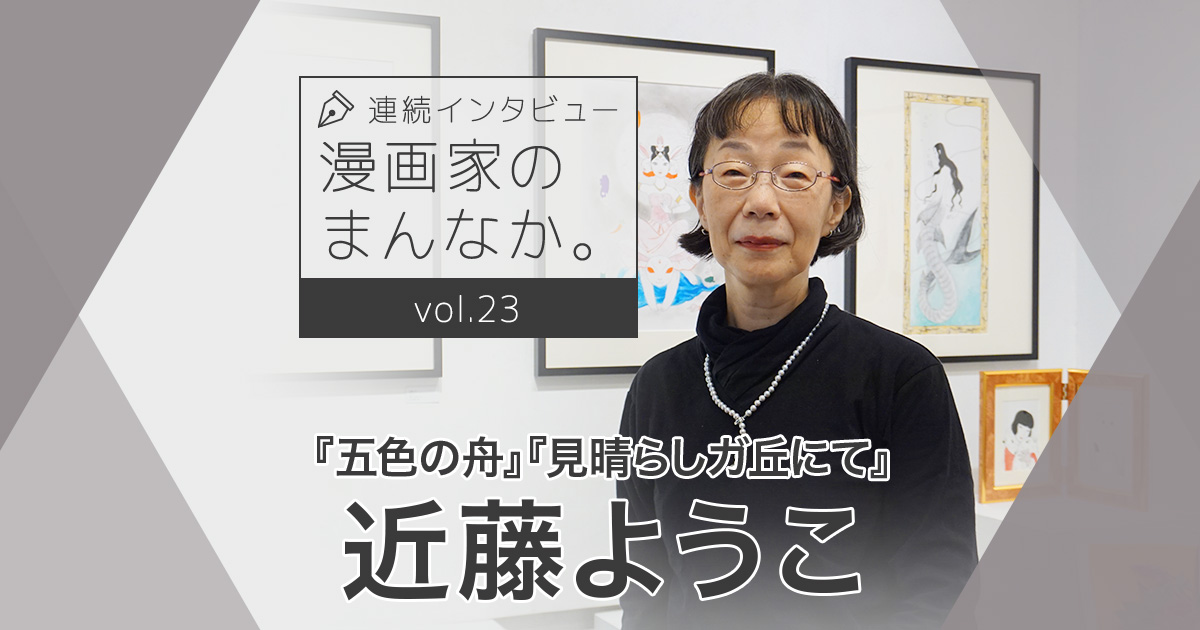漫画サンデー元編集長が舞台裏を語る! 上田康晴「マンガ編集者 七転八倒記」 ACT.7 昼は三枚目、夜は三代目

※本ページは、2013年11月~2015年5月にeBookjapanで連載されたコラムを一部修正、再掲載したものです。
▼プロフィール
上田康晴(うえだ やすはる)
1949年生まれ。1977年、実業之日本社に入社。ガイドブック編集部を経て、1978年に週刊漫画サンデー編集部に異動。人気コミック『静かなるドン』の連載に携わる。1995年に週刊漫画サンデー編集長、2001年、取締役編集本部長、2009年、常務取締役を歴任し、2013年3月に退任。現在、フリーのエディター。
ACT.7 昼は三枚目、夜は三代目
1994年には映画につづいて『静かなるドン』はテレビドラマになった。日本テレビ系の『西遊記』(堺正章、夏目雅子出演)が終わり、『静かなるドン』に白羽の矢が立った。金曜・夜8時という、かつては大ヒット番組、石原裕次郎の『太陽にほえろ』が放映されていた時間帯である。いわゆるゴールデン・タイムだった。
しかしその後、時の流れとともに、この時間帯は、必ずしもゴールデン・タイムではなくなっていた。「この時間帯で視聴率をとるのはかなり難しくなっている」とはテレビ業界に詳しい人が語っていた。
決して甘い時間帯ではなくなっていたが、私には、不思議にヒットの予感があった。『静かなるドン』のことをよく知っているスタッフ(香川照之主演でドンをヒットさせたメンバー)が制作に加わっているという安心感と、この作品の力を信じていた。
また、この連載のスタート時に、新田作品にほれ、最初に担当した作品が『家庭にほえろ』だったと書いたが、この作品のタイトルは『太陽にほえろ』を意識したものだった。その『太陽にほえろ』と同じ時間帯でその新田氏の作品が放映されるということにも、なにか縁に似たツキを感じた。
ただ、ドン役に中山秀征と聞いたときには、今度はイメージが映画の香川照之さんと違い過ぎ戸惑った。しかしドラマが始まってみると、これまた杞憂であったことを思い知った。漫画にはない、また香川照之さんとは違った、独自のドンを見事につくりあげていたのだ。
中山秀征さんは、『「静かなるドン」完全データブック』(週刊漫画サンデー編集部・編)の中で次のように語っている。
「ヤクザを演じられる役者はいても、下着屋もできる役者はなかなかいない。だから秀ちゃんだよ―。ボクを近藤静也にキャスティングしてくれた日本テレビの『静かなるドン』担当プロデューサーの言葉です。当時のボクは、音楽ではロックンロールに夢中になっていて、テレビではバラエティーの秀ちゃんでやっていました。この二面性が担当プロデューサーの目に止まったのです。(中略)『昼は三枚目、夜は三代目』が番組のキャッチフレーズで、なかなかうまいコピーだと感心したものです。変身願望は誰にもあるものですが、『ウルトラマン』や『仮面ライダー』のようなスーパーヒーローではない、生身の人間が昼と夜とで姿を変えるところにヒットした要因があったように思います」
たしかに『静かなるドン』の特徴をみごとにとらえたキャッチだ。この担当プロデューサー、雑誌の編集センスも兼ね備えていたように思う。
しかし一番驚いたのは、やはりこのドラマの主題歌である。初めに桑田佳祐と聞いたとき、思わず「どこの桑田さんですか?」と聞き返したほどだった。にわかに信じがたく、それだけで舞い上がりそうだった。以来、漫画サンデー編集部では、カラオケ店に行くと必ず、『静かなるドン』の主題歌『祭りのあと』を全員で合唱したものだ。
ドラマは、視聴率が12%から14%をキープして大成功。2クールを無事終え、ドラマの打ち上げは明治記念館でおこなわれた。出演者が全員参加の中に桑田佳祐さんの顔もあった。同じ歌手仲間のなぎら健壱さんも出演者として参加していた。桑田さんの先輩にあたるなぎら健壱さんに対して、丁寧に挨拶していた姿が印象的だった。どこまでも謙虚な人だった。

『静かなるドン』 ©新田たつお/実業之日本社
二次会では、中山秀征さんの司会で大カラオケ大会となった。歌自慢の素人が、中山さんの軽妙な話術にのせられ、ステージに上がっていった。その中になんと、わが社の漫画大好き制作部長・Oがいた。その度胸には驚いた。しかし選曲がよくなかった。チャゲ&飛鳥の「SEY YES」。フジテレビドラマ『101回目のプロポーズ』の主題歌。この会場にいるのは、日本テレビの面々。即ダメ出しの鐘が鳴らされた。そんなご愛嬌の後、サプライズが……。突然、桑田佳祐さんがカラオケをバックに『祭りのあと』を生で披露してくれたのだ。感動のあまり思わず新田たつお氏と握手をしていた。毎日毎日、まさに命を削るような思いで『静かなるドン』を描きつづけてきたことが「やっと報われましたね」と伝えたかった。 この日、しばし感動は冷めやらず、夜を徹して飲んだ。 (つづく)
関連書籍