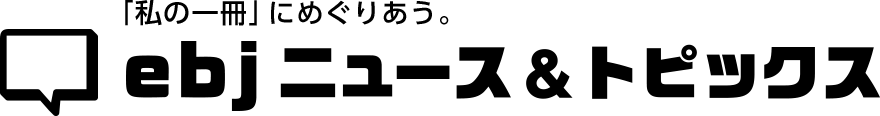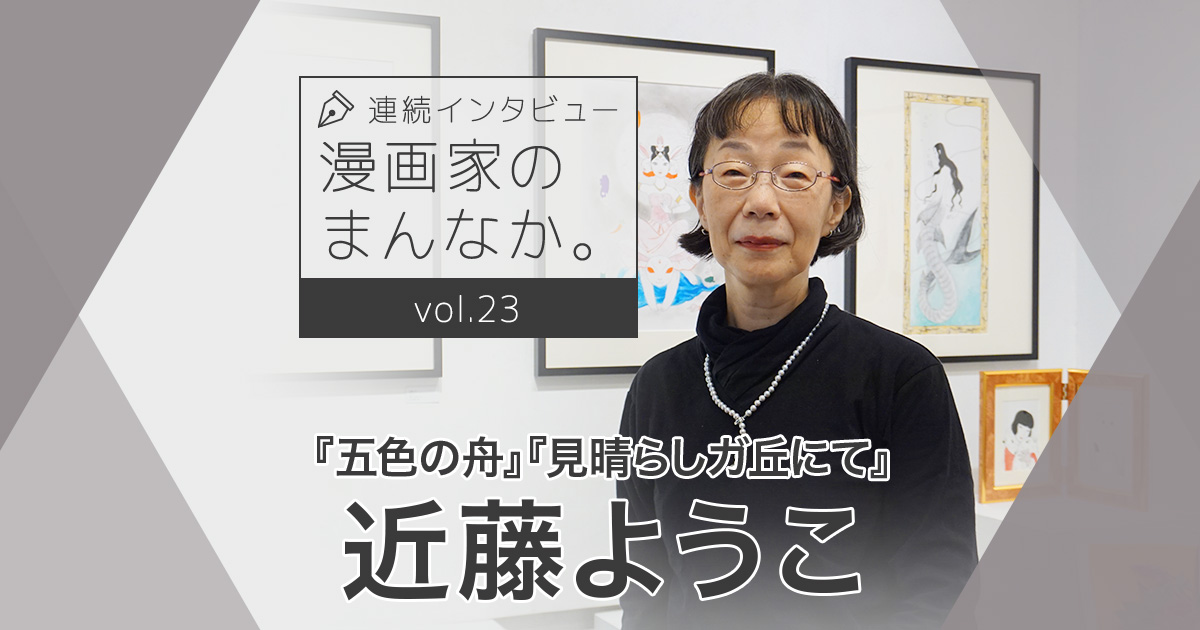漫画サンデー元編集長が舞台裏を語る! 上田康晴「マンガ編集者 七転八倒記」 ACT.5 漫画家は本好き映画好き

※本ページは、2013年11月~2015年5月にeBookjapanで連載されたコラムを一部修正、再掲載したものです。
▼プロフィール
上田康晴(うえだ やすはる)
1949年生まれ。1977年、実業之日本社に入社。ガイドブック編集部を経て、1978年に週刊漫画サンデー編集部に異動。人気コミック『静かなるドン』の連載に携わる。1995年に週刊漫画サンデー編集長、2001年、取締役編集本部長、2009年、常務取締役を歴任し、2013年3月に退任。現在、フリーのエディター。
ACT.5 漫画家は本好き映画好き
前回、『まんだら屋の良太』に関して文学好きの編集者にファンが多かった、と書いたが、畑中純氏はじめ、いままで出会った漫画家に共通していたのは、本をよく読んでいたこと。さらに映画にもうるさかった。
「少年ジャンプ」で活躍していた某漫画家は、デビューのころ、担当の編集者から日本の古い映画を観るようにすすめられた、という。まだ銀座に並木座という老舗の映画館があったころの話である。彼の作品から、小津安二郎や黒澤明に影響されたことを読み取ることは難しいが、カメラアングル、役者の演じる表情、ストーリーのテンポなどが勉強になったとか。
読書や映画鑑賞の効用は、ひとりの人間では経験できない多様な人生を疑似体験できること、と言った先達がいたが、これは、漫画家にとっても必要不可欠の条件かもしれない。生前、赤塚不二夫氏は手塚治虫氏から「漫画は読まなくてもいい。いい音楽を聴き、本や映画を見なさい」といった意味のことをよく言われたという。
赤塚氏がこよなく愛した映画は『第三の男』だった。新宿・下落合のお宅にお邪魔したときのこと。大きな白いスクリーンを壁一面に広げ、「こんど、これで映画を見せてあげるよ」と、そのスクリーンを自慢していた。自然に話は好きな映画に……。そして『第三の男』についての講義と相成った。焼酎のお湯割りをチビチビ口にしながら、独自の映画論は尽きなかった。私も一緒になって、お酒を飲んでいたので、はっきりとは憶えてないが、陰影の使い方の上手さを盛んに言っていたように思う。
私が「この映画はテレビで観ました」なんて不用意に言ったところ、「映画館の暗がりで、しかも大きなスクリーンで観なきゃダメだよ」と怒られてしまった。この時、「こんど、わが家のスクリーンで見せてあげるよ」と言われたが、赤塚氏はまもなく入院してしまい、この約束は実現しなかった。
その後、スクリーンで『第三の男』を観ることは叶わなかったが、DVDで最近再び観る機会があった。そして、観るたびに新しい発見があることに気が付いた。赤塚氏の気持ちに少しだけ近づいた気がした。
そもそも赤塚氏と親しくお付き合いできるようになったきっかけは、『静かなるドン』だった。もちろん以前から、会社として仕事上の繋がりはあったが、私が「週刊漫画サンデー」に異動したころには、赤塚氏の連載はなく、疎遠になっていた。それが、赤塚邸を親しく行き来できるようになったのは、赤塚夫人をはじめ赤塚氏の周囲にいるスタッフが『静かなるドン』のファンだったからだ。「一度、作者の新田さんに会いたい」ということから赤塚家と新田家の交流が始まった。特に新田氏担当の私は、事あるごとに下落合の赤塚邸に出向いた。そして酒盛り。赤塚邸は人の出入りが盛んで、時折、知らない人が我が家のような顔をしてデーンと座っていた。あとから「そういえば、あの人、テレビに出ていたな」なんて気が付くことがよくあった。特に自己紹介をするわけでもなく、赤塚氏の知り合いというだけで、お互い納得していた。今思うと、不思議な飲み会だった。とにかく赤塚氏は、とことん善人だった。来る人拒まず、だった。私みたいな新参者を一人前の編集者として遇してくれた。

『静かなるドン』 ©新田たつお/実業之日本社
赤塚夫人の真知子さんは、『静かなるドン』に出てくる主人公静也の母親・妙に似ていた。そんなことからかどうかは、憶えていないが、漫画サンデーの巻頭カラーページに妙の扮装で出てもらったことがあった。ドンの役はもちろん赤塚不二夫氏。撮影当日は、それらしき雰囲気の日本間を借りで撮影が行われた。このようなお遊びは大好きの赤塚氏。この時は、刀を持ち大はしゃぎ。かなりその気になっていた。そういえば、このためにスタイリストの人にもお願いし、まるで本格的な映画の撮影状態だった。赤塚氏が張り切ってくれた分、かなりサマになった絵ができた。
このように、天才・赤塚不二夫氏をはじめ夫人、スタッフに愛された「静かなるドン」は、そのあとも、いろいろな人たちを結び付けてくれた。(つづく)
関連書籍