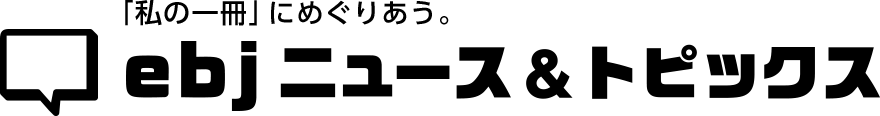昭和のテンプレ夫婦の真実の姿とは?『真綿の檻』とは出られそうで出られない家族の呪いのことだ
人を表面的な印象だけで判断してはいけない。夫や実家に尽くしてばかりに見える妻と、妻をこき使うオレ様な夫。昭和の頃からよくある夫婦のテンプレのような二人。そんな夫婦の真実の姿を描いた『真綿の檻』を読むと、そう感じる。

「優しそう」「古風で昭和な嫁」に見える妻・榛花(はるか)と、夫・一広。この夫婦について弟夫婦、両親の目線から語られる。

『真綿の檻』©尾崎衣良/小学館 1巻 1話より
榛花はフルタイムで働いているにもかかわらず、家事のほとんどを完璧にやっていて、彼女の弟夫婦が家に行くと、妻が甲斐甲斐しくキッチンで動いているのに対し、夫は何もしていない。「まるで昭和の夫婦って感じ」と義理の妹は話す。
榛花の母親が骨折したという連絡が来ると、弟はこう言う。姉は「承認欲求が強いタイプ」だからと。昔から文句ひとつ言わず、必死に母の手伝いをしていた姉は、きっと誰かに褒められたいのだ、そう弟は思っていた。

『真綿の檻』©尾崎衣良/小学館 1巻 1話より
榛花の母親は、娘に対しこう思っていた。「あの子は私と同じ」。母親は、家のことは介護も含め、全て夫から押しつけられていたけれど、まったく感謝されない生活を送っていたのだ。

『真綿の檻』©尾崎衣良/小学館 1巻 2話より
自分が苦労した分、娘に家のことを厳しく教え込んだ母。今では立派に家事をこなす娘を見て、自分の苦労が報われたと思っていた。
そして、榛花の夫。妻の実家に一緒に行くと「榛花に実家に来てもらって母親の面倒を見てもらおう」と家族会議で決まると、こう言う。

『真綿の檻』©尾崎衣良/小学館 1巻 2話より
大人なんだし、ご飯くらい自分で作ったらいいのでは、と困惑する家族。この夫は、家事が本気で何もできないのか…!?
妻が虐げられているように見える夫婦の話かと思うと、予想外の展開に自分が持っている思い込みを思い知らされるラスト。それは、夫婦の周りにいる家族たちが持っている思い込みそのままだ。
タイトルの『真綿の檻』というのは、そこからすぐに抜け出せそうでなかなか抜け出せない家族のことなんじゃないだろうか。「真綿で首を締める」というけれど、一見、柔らかそうな綿でもじわじわ首を締めることができてしまう。本作には「昔から家族に言われてきた言葉や、家族内での役割に囚われ続けている大人たち」がたくさん出てくる。それも無意識に囚われているので、本人は気づいていない。
作者の尾崎衣良さんは『深夜のダメ恋図鑑』で、少女マンガらしい美麗な絵柄とうらはらに、ダメ男子をぶった斬るキレッキレな女子たちを描いた。今回も「真綿の檻」に囚われている人たちに向けて「早く目覚めろ!」と次々にぶっ叩いていくようなストーリーに、尾崎先生、さすがだ! と拍手をおくりたくなるのだ。