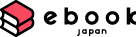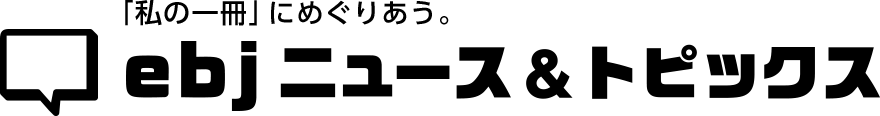『Psycho-Party』あなたをサイキックワールドに引き摺り込むその“絵”に刮目せよ

描かれた1枚の絵が、作品の印象をガラリと変える時がある。そのようなページに出会った時は大抵、ページをめくる手が止まり、鳥肌が立つ。そうした感動にまた出合いたくて、私は漫画を読んでいるのかもしれないとさえ思う。
『Psycho-Party』では幸運にも、第1話のラストに“その瞬間”が訪れた。

カートゥーン調の絵とシビアな世界観のギャップ
本作はとある事件がきっかけで、超能力者(サイキック)の存在が公にされ、その存在が危険視されている世界が舞台。主人公の少女・ヒバナは幼い頃、その“とある事件”が発端となり家族がバラバラになった過去を持つ。
ヒバナは特別な事情を持つ子供が引き取られる「ブルーリボン養護院」で暮らしているが、生来の気の弱さから他の子供からいじめられており、体には痛々しい傷も刻み込まれている。

『Psycho-Party』©ナガサワヒロ/芳文社 Chapter1より
シビアな主人公の状況だが、相反して絵柄はカートゥーン調のデフォルメが効いた可愛らしい絵柄で、このギャップが作品全体の印象を和らげ、作品を誰もが読みやすいものにしている。
「“顔”が見えない」がもたらす緊張感
特徴的な絵柄以外にも『Psycho-Party』の絵には特筆すべき特徴がある。それは「表情を描かない」ということ。『Psycho-Party』では主要人物やモブキャラを問わず、ところどころで人物の顔を、全面黒でベタ塗りをすることがあるのだ。
作画コストの面からそのようにしているのかは判らない
しかしこれにより登場する人物の“表情が全くわからない”状況が度々発生する。そしてその人物が信頼できるか否か、顔の表情がわからないだけでたちまちわからなくなってしまうのである。「“顔”が見えない」ことが作品全体に絶妙な緊張感をもたらしているのだ。
しかも、顔のベタ塗りがあらゆる人物に適用されているので、ヒバナに近しい人でさえも、どこか信頼できなくなってしまう時がある。これが、ある種読者への警告のようにも受け取れて面白い。

『Psycho-Party』©ナガサワヒロ/芳文社 Chapter1より
◉第1話の最後に待っているもの
1話では、超能力者と超能力者を危険視する組織が登場する。因みに、それに対峙するようにそれ以降の話では超能力を研究し利用しようとする組織が登場する。かのように本作では超能力者をめぐる世界の状況とともに、ヒバナが周囲の思惑に巻き込まれていく様子が描かれる。
第1話に話を戻そう。ヒバナは、ひょんなことからゼッカという女友達ができるが、ゼッカはヒバナの“特別な事情”を利用しようと近づいた、超能力者排斥組織のメンバーだった。裏切られたヒバナはゼッカに迫るが、ゼッカは冷たく、しかし思った以上に強くヒバナを押し返してしまい、ヒバナは気を失う。
そして、次のページをめくる……。

『Psycho-Party』©ナガサワヒロ/芳文社 Chapter1より
正直、それまでは前述した絵のユニークさは面白いと思っていたが、物語自体にのめり込んでいるとは言い難かった。その一番の理由は、物語の現在の時間軸では“誰も超能力を使用していなかった”からであろう。物語のキーとなる「超能力」がどんなものなのか、いまいち把握できないことが、作品に対してどこか曖昧模糊とした印象を抱くことにつながっていた。
しかし、その思いは、一瞬にして覆される。
次のページには私が「待ち望んでいた」ものではなく、「想像以上」の絵が描かれていた。言葉はいらない、物語における絵が放つ「力」にあふれた絵を見て、私は『Psycho-Party』の世界に、一気に引き摺り込まれた。
その“絵”は、あなた自身の目で確かめてほしい。
ノンストップで物語が展開していくスピード感も大きな魅力の『Psycho-Party』。めまぐるしく変わっていく事態に翻弄され続けるヒバナ同様、我々読者も、物語の全容を掴めないまま読み進めていくことになる。

『Psycho-Party』©ナガサワヒロ/芳文社 Chapter3より
誰が彼女を守ろうとし、誰が利用しようとしているのか、そして、それぞれの目的は一体何なのか。一見かわいらしくも、ミステリアスで危険な雰囲気に満ちたこの物語は、1ページ、1ページをめくる楽しさを、思い出させてくれる。
執筆:ネゴト / Hiraki Rihei