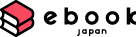かわぐちかいじ先生に独占インタビューを敢行、デビュー前夜から話題作『空母いぶき』まで、創作に関わるエピソードをたっぷりお聞きしました!!
●二人で目指した漫画家への道
――かわぐち先生の漫画との出会いをお聞きできますでしょうか。
かわぐち
僕は1948(昭和23)年生まれなのですが、物心がついた頃には、手塚治虫先生の漫画とか、「少年画報」「冒険王」といった月刊の漫画雑誌が出ていました。自分の家では買ってもらえなかったので、床屋さんや駄菓子屋さんなどに置いてあるのを読み始めたのが最初ですね。まだ「週刊少年マガジン」や「週刊少年サンデー」などの週刊漫画誌が出る前で、月刊漫画誌の時代です。
10歳くらいの時、
『鉄腕アトム』や
『鉄人28号』、
『赤胴鈴之助』『イガグリくん』
『矢車剣之助』などのキャラクターに憧れて、双子の弟といっしょに、二人で漫画を模写することに熱中しました。

双子だったので、二人で「どちらが上手い?」と切磋琢磨できる環境だったのが、よかった気がします。これが年の離れた兄弟だったら競う相手になりませんから、すぐに飽きていたかもしれません。お互いに隠れて練習したりして、妥協せずとことんまで競争していました。
中学生くらいになると、模写に飽き足らなくなってきて、「自分で漫画を描こう」という方向にいくんですね。二人とも、まだ漫画はペンと墨で描くんだというのを知らなかったので、大学ノートに鉛筆で描いていました。映画風にお互いに「プロダクション」を作って、それぞれのキャラクターを所属俳優のようにして漫画を描いたり、時々キャラクターを交換したりしてね。
やがて高校生くらいになると、青林堂から「ガロ」、虫プロから「COM」が創刊されて、漫画の新人賞というものを募集していると知ったんですね。じゃあ、二人で新人賞に応募しようということで、虫プロの「COM」に兄弟が共作で描きはじめたんですが、張り切りすぎてうまくいかず、途中で挫折してしまった。兄弟合作は一本でやめたんですが、ペンでの描き方がわかったので、遊びじゃなくて、プロの漫画家になりたいという気持ちが芽生えてきたのがこの頃です。
当時、「週刊少年サンデー」「週刊少年マガジン」が出始めた頃でしたが、二人とも高校生になっていたので、少年雑誌ではなく、貸本漫画の「日の丸文庫」や「魔像」、平田弘史さん、さいとう・たかをさん、ケン月影さん…こういった青年漫画の方に惹かれていたんです……特に、永島慎二さんの 『漫画家残酷物語』には非常に影響を受けました。
それまで知らなかった漫画家の生活が、とてもリアルに描いてあり、「漫画家の現場はこんなに楽しくて、こんなにつらくて、魅力的なのか…」と、僕たちのような漫画家になりたい青年たちを強く惹きつけたんですね。この作品を読んで、決定的に漫画家になりたいと思うようになりましたね。
●名門・明大漫研から在学中デビュー
――デビューのきっかけはどういう経緯だったのでしょうか?
かわぐち
「とにかく、東京に行って、漫画の世界に触れないとチャンスはない」と思ったので、東京の大学に入ろうと、一旦は漫画から離れ、二人とも受験勉強に身を入れることにしました。
僕は明治大学に入学し、「漫画研究会」に入ったのですが、弟が入学した大学には「漫研」が無かったんです。自分で同好会を作ろうとしたのですが、結局バンド活動を始めてしまったので、漫画からは遠ざかってしまいました。
僕が入った明治大学の「漫研」は、伝統のあるサークルで、漫画を描く環境には非常に恵まれていました。当時は、けっこう真面目に描いてましたね。
この頃は、青年漫画誌がバンバン創刊されていた時代で、大学の漫研の先輩の中にも、青年誌の編集者になる人がけっこういました。
とにかく青年漫画の描き手が足りない状況でしたので、大学3年の時に、少年画報社に入った先輩から「『ヤングコミック』で描いてみないか」と、声をかけてもらったのがデビューのきっかけです。何度もボツを食らいながら、執念深く描き上げて、最初に掲載されたのが、当時、盛んだった学生運動の現場を題材にした青春群像を描いた『夜が明けたら』という12ページの作品でした。
今のように、まず新人賞に応募して、そこから担当編集者がついて…というような苦労はなかったので、ラッキーといえばラッキーなのかも知れませんが、大学の先輩が担当編集というのも、やりにくさもありましたね(笑)。
●跡継ぎ問題と週刊誌連載
――漫画家になると決めた時、親に反対はされなかったのですか?
かわぐち
弟と二人で勉強しないで漫画ばかり描いていたので、叱られることはありましたが、身を挺して漫画家になるのを阻止する、という程ではなかったですね(笑)。というのも、卒業後、僕と弟のどちらかが、東京から帰ってきて父親の商売を継ぐという条件がありましたので、好きにさせてくれていたんですね。
二人とも、東京では勉強そっちのけで活動していたのですが、結局、漫画家としてデビューできた僕の方が、東京に地盤を作ったわけですね。弟の方はバンド活動ですから、親には遊んでいるように見えたかもしれない。
漫画家も、親から見たら浮き沈みがあるし、不安もあったんだろうけど、曲がりなりにも原稿料が入ってくるので、親からの仕送りをストップして、逆に親に仕送りをしていた。弟にも小遣いをやったりして、「俺は稼いでいるんだ」とアピールしていました。
弟は相当反発していたんですが、二人で話し合って、最終的には弟が実家に帰って家業を継ぐことになったんです。それが22歳の頃でした。
――漫画家としてやっていけると、何かを掴んだと感じた作品はありますか?
かわぐち
最初はトントン拍子というわけには行かなかったですね。「ヤングコミック」でデビューして、何本か読み切りや、連作などを描いていたら、芳文社の「週刊漫画TIMES」から「週刊誌でやってみないか」という話が来まして、不定期連載をいくつかした後、
『唐獅子警察』
という北海道のヤクザの話を原作者の滝沢解さんと組んで、週刊連載しました。
ヘトヘトにはなったんですが、人気も悪くありませんでしたし、曲がりなりにも週刊連載を乗り切れることができた。このことで、この先も漫画家としてやっていけるな、と思いました。それが、24、5の時ですね。
●『沈黙の艦隊』『ジパング』『太陽の黙示録』…『いぶき』に至る大作ロマン!

―― 社会現象にまでなった 『沈黙の艦隊』という作品は、どのような発想で生まれたのでしょうか。
かわぐち
「モーニング」で『アクター』という芸能界ものを連載している時、モーニングが隔週刊から週刊になったんです。編集長がテコ入れをしたい、ついては「『アクター』に負けないような話題性のある作品をやりたい」と。
『アクター』は講談社漫画賞も取った作品で、自分でも手応えもありましたし、編集長も気にいっていたのですが、ずっと続けらていられるような話でもなかったので、終わらせて新連載を立ち上げることになりました。
僕は父親が海軍出身だったので、よく連れられて戦争物の映画を観ていました。当時、雑談の中で、ドイツのUボートとか、映画『眼下の敵』とか、潜水艦が好きだという話をしたことがありました。編集長との打ち合せの際に、「潜水艦の話はどうかな」と編集長の方から持ちかけてきたんです。
打ち合わせの中で、第二次世界大戦の「Uボート」とか、「伊号潜水艦」などの話ではなく、現代の話にしたいと意見が一致しました。そこで、「日本は原子力潜水艦はおろか、原子力のエンジンを積んだ艦船も持てないから、アメリカと日本が極秘で建造したということにしたらどうか…」といったことを話し合っているうちに、これはいけるな、と手応えを感じましたね。
そうして1988年の5月か6月くらいに話が決まり、夏からの連載に向けて描きはじめていたんですが、ちょうど「なだしお事件」が起こったんです。
――海上自衛隊の潜水艦なだしお号と衝突して遊漁船が沈没した事件(1988年7月23日)ですね。
かわぐち
打ち合せをしていたら、「何か潜水艦のニュースをしているぞ」っていうんで、驚いてテレビをつけたら、自衛隊の潜水艦が衝突事故を起こし、しかも犠牲者が出ているという…。
『沈黙の艦隊』の第一回は原潜が浮上してくるシーンから始める予定でしたから、「これは大変なことになった」となりまして、編集長から「ちょっと様子を見よう」と。結局、9月下旬ごろまで連載開始を伸ばすことになりました。
――しかし、始まってみると大ヒットしましたね。
かわぐち 僕も、編集部も最初から「これはいけるな」と。今までの青年雑誌の漫画にはない独自の路線でいけるんじゃないかという手応えがありましたね。それを6年から7年続けていったのは大変でしたが(笑)。
原子力潜水艦が「国家」として機能するというのは、最初からアイデアがあったのですか?

かわぐち
いえ、途中からですね。日本とアメリカの技術を結集して極秘に建造した潜水艦が脱走し、日米がそれを追いかけて追いかけ、「その潜水艦とは一体何だったんだ」ということが明らかになっていく、といったくらいのことを考えていたんです。公にできない問題を抱えた「犯人」が逃げ出して、それを秘密裡に追う「刑事物」ですね。
でも、それではドンパチやったらお終いなんですよね。日米が協力して、潜水艦包囲網を作ったとしたら、どうやっても逃げられないから、閉じ篭って終わりになってしまう。
せっかく良いジャンルで、当時の青年誌界にはないような世界がうまく描けているのに、これはすぐ店を畳まなければならなくなる。
「この世界をうまく続けられないか?」と僕と編集長と担当と3人で必死に考えたんですよ。そしたら編集長が「『独立国家』にするのはどうだろう」と。
そうすれば、潜水艦戦のドンパチだけじゃなく、国家間の政治を含めた、もっと広い世界が描けるんじゃないかと。
で、「やまと」を独立国家にしたら、そこから話が広がりましたね。内密に捕らえてすぐ終了というわけにはいかなくなる。そうすることで「公」の話になるわけですよね。世界に知れ渡ることで、日米が内密で「臭いものに蓋」をすることはできなくなり、主人公の海江田が訴えることを、まともに相手にしなくてはいけなくなる。話がどんどん広がって、面白くなったと思います。
●とにかく、次に出る作品を面白く!
――『ジパング』『太陽の黙示録』なども、何十巻に及ぶ長編ですが、結末は考えておられないのですか?
かわぐち
そうですね。ある程度のイメージみたいなのはあるんですが、そこに行く道筋はまったく違うものになりますね。
というのも、週刊誌だったら、先の話は先の話としてひとまずおいて、まず今週や来週――もっといえば、来週なんてどうでもいいから、今週をとにかく面白くしたいという気持ちの方が大きいんです。今週が面白くなったら、その次も絶対に面白くなるから。
今週がつまらなかったら、次の2週、3週は絶対にうまくいかない。
――読んでいて、「えっ! これをやったら取り返しがつかなくなるのでは」という場面がたくさんありますね。
かわぐち
そういうふうにしたいんです。漫画はそういう「どうなるの!?」という「取り返しがつかないこと」を考えなければいけない。あーだ、こーだと考えて、「とにかく、次に出る作品を面白くしていこう」と必死に考える。先のことはとりあえず、どうでもいい(笑)。
もちろん、ある程度ゴールのようなものは見えているんだから、そこにたどり着けばいいんで、とにかく眼の前の作品を面白くすることを心がけていますね。
●「今の日本」に抱えているストレスを解消したい
――『沈黙の艦隊』『ジパング』『太陽の黙示録』『空母いぶき』などは、いずれも「もう一つの日本」を出現させて、日本を語っていくという作品でありますが…
かわぐち
はい。自分もそうだし、僕らの年代は、みんな相当に、今の日本にストレスを抱えていると思うんですよね。「日本は本当にこれでいいの?」というストレスを。でも、「じゃあ、良くないのなら、どうすればいいの?」というのは、はっきりわからない。これもまた、ストレスなんですよね。
だから、それを作品の中で描いて、ストレスを解消したいなというのがあるんですよね。今の日本の状況で「ここがダメ」「あそこがダメ」というのがある程度わかるとしても、それをどう解決すれば、良いと思える日本になるのか、という。それは多分、僕らの世代は、みんなその問題を抱えてますよね。
そこを、ドラマにしたいなと。みんなでそこを感じられればいいかな、というのは、常にありますよね。そういうのがないと面白くないですよね。
とはいえ、正直なところ、自分も考えながら描いているので、最初から自分の中に「こうしたらいい」という正解の道が自分の中に出来ていて、それを絵解きしていく…という感じではないんです。
●驚異の週刊と隔週2本連載の秘密!
――先生の作品はスケールの大きな物語が多いですが、やはり壮大な物語を描きたいという願望があるのでしょうか?

かわぐち
これは、自分の描くキャラクターの絵柄から来るものもあるんですよね。自分の描く絵の世界は、デフォルメが効いて誰が読んでもすごく面白いキャラクターを描くタイプじゃなくて、どちらかというとリアルなキャラクターで、ストーリーを語っていきたいタイプなんですよ。そうなると、リアルなキャラクターで日常生活の淡々とした状況を描くよりも、極限状況の中におかれて「じゃあ、ここからどうするんだ?」という荒唐無稽なストーリーの方が、劇的に面白いですよね。
いつもわりと極限状況を考えたりするんですよ。「主人公たちがどういう状況に陥っていくか」という設定から入っていって、「じゃあ、困った、大変じゃないか」という状況を作り、それをどうやって切り抜けていくかを考えていく。そうすると、自分が描くようなリアルなキャラクターでも、面白い漫画になりそうだなと思うんですよ。
荒唐無稽な設定でも、キャラがリアルだと、話もリアルにならざるを得ない。キャラクターがリアリティを要求するんだよね。作者としては、その要求に応えなきゃいけないんで、大変ですけどね。
それを可能にするのは、スタッフの画力の力もあるんですよね。僕の場合は、長年やってくれている上手い人が揃っているので、スタッフがリアリティを失わない画力と知識を持っていて、とても助かっているんです。
――長らく、週刊誌1本と隔週誌1本で同時連載されておられますが、ひと月に約6本を仕上げられるというのは凄まじいですね。
かわぐち
これも、やはりスタッフの総合力、スキルです。それがないとできないですよ。全ての画のリアリティを、とても自分一人では管理できないんですが、戦艦とか兵器が好きなスタッフがいて、そのリアリティを管理している。たとえば「『せとぎり』という護衛艦の内部はどうなっているか」とかも、スタッフが調べて描く。もちろん調べられるところまでですが、ギリギリわからなくも「多分こうだろう」と推測して描くことができる。
そういう「好きな」スタッフの知識とスキルのおかげで描ける…というか、それがないと連載を続けられないですね。
●『空母いぶき』、その征き先は!?
――現在「ビッグコミック」に連載中の『空母いぶき』は、それまでの自衛隊を舞台にしたものとは違い、尖閣諸島をめぐる中国との攻防という、非常にリアリティのある設定になっていますね。
かわぐち 同じ自衛隊ものでも『沈黙の艦隊』と『ジパング』は、「自衛隊のリアリティ」と、「物語の面白さ」というのを合体させたいという思いがあったんですが、『空母いぶき』は、「物語の面白さ」というよりも、自衛隊そのものを題材に、もしこんな状況になったらどうなる? っていうところを、やるしかないな、と思ったんです。それで、タイムスリップのような「物語」をでっち上げるということではなく、もし今、実際に中国が尖閣領有のために武力行使してきたらどうなるのか、というのをシミュレーションしてみて、できるだけリアルにやりたいと考えたんです。

それで僕の友人でもある自衛隊に詳しい軍事ジャーナリストの惠谷治さんと相談しながら、とにかく自衛隊に関すること、自衛隊が戦うとこうなるといったところは、できるだけリアルに、嘘をつかないようにしたいなと思いながら描いています。
『沈黙の艦隊』や『ジパング』の時は、「物語の面白さ」のためにある程度リアリティが犠牲になってもしょうがないと思いながら描いた部分はあるんですが、今回はそこを逆転させて、みんなが読んで「これはリアルだな」と受け取ってくれるように、できるだけ戦闘の状況で荒唐無稽にならないように心がけて描いています。
――現実で様々な事件が起こったり、世界情勢が変わったりして、これを入れておければよかったのに、と思われることはありますか?
かわぐち 一応、「20XY」年という架空の年代にはなっているんですよ。これが来年なのか、10、20年先なのかはわからないようにしているんです。だけど、リアルな話なので、安保法制とか、日米の政治状況がどんどん変わってきていますよね。連載開始時は、米国大統領はヒラリー・クリントンを想定して描いていたら、まさかのトランプが大統領になったりして。「これは困った」とは思いました。
――『空母いぶき』は、まだ序盤といったところですが、今後の展開のヒントをいただけますか?
かわぐち
一つ描けると思ったのは、「人間と武器のつきあい方」ということですね。これって、なかなか解決されないじゃないですか。人間は武器を捨てられない。そして、武器というのは日々更新されて新しくなっていく。竹槍から、ミサイルまで行ってしまう。その武器と、人間は付き合わざるをえない。
「人間は武器とどう付き合うのか」というテーマは、リアルな世界でなければ描けない。それは、今『いぶき』を描いている中に、ある程度は盛り込んでいきたい。「答えはこうだ」という最終的な答えを示すところまでいけなくても、自分の中で葛藤しながら、「この道筋を行けばなんとかなるんじゃないのか」というのが一条の光でもいいから提示することができたら、成功なんじゃないかと思います。
●毎回毎回、自分の中のハードルを超える作品を創る
――漫画を描く上で失ってはいけないというものは?
かわぐち
そうですね。毎回、1話24ページの中で、自分が設定した「ハードル」のようなものがあるんです。
それは、単純に面白いか、面白くないかということだけでなく、例えば自分が「この1話を読むために、360円する雑誌を、お金を払って買う価値があるか」、そのレベルに達しているかということを考えます。これだったら360円払えないなあ、といったレベルにはしたくないんです。
毎回、同じようなストーリー展開ではなく、その回ごとに「キャラクターの心情が掘り下げられて面白い」という展開や「ストーリーがものすごく劇的になっていく」とか、「その極限状態をどうやって脱出するのか」など、その回ごとに毎回違っても、様々な面白さがある。そして、その回の劇の深みをうまく表現できているかによって、自分の設定した「ハードル」を超えるか超えられるかが決まる。そういう自分の中の「ハードル」を、毎回、超えられているのか、というのが一番気になりますね。

漫画を描いている方は、みんな自分なりの「ハードル」があって、それを超えるためにひたすら日夜努力しているんじゃないでしょうか。
あと、読者をナメないというのも一つですね。「もういいや、これでわかるだろう」という態度になるとマズいなと思います。
――来年は漫画家生活50年ですね。読者を飽きさせず、ずっとトップを走っておられますが、秘訣のようなものはありますか?
かわぐち
あっというまですね。今、どこの編集部も「こうして欲しい、ああして欲しい」という注文が多くなりました。その注文を聞くのが大変なんですよ(笑)。
でも、そこが「若返り」の秘密なんです。聞く耳を持って、それに応えようとする。そうすると、わりと新人の頃の感覚に戻れてるんです。そこはありがたい。
「すごいですね、先生」と毎回やられるとダメになりますね。
なぜ編集者の注文が多くなったかというと、僕が聞くからなんです。それは、体力を保つ秘訣かな(笑)。
――読者の方、ファンの方にメッセージがありましたら。
かわぐち 『空母いぶき』は、すごい展開になりますので、お楽しみにしてください。
――それは、すごく楽しみですね! ありがとうございました。