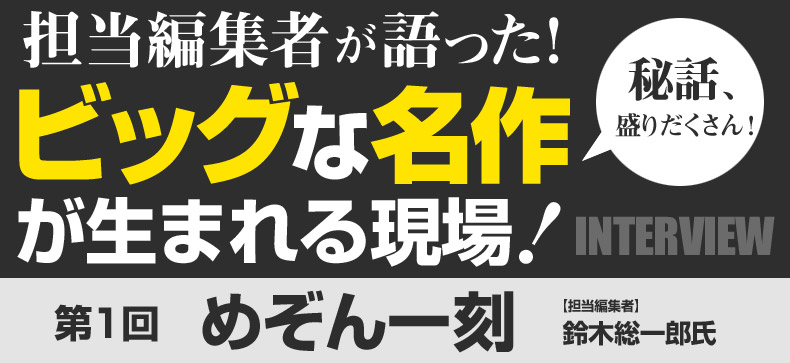
※当時の内容をそのまま掲載してます。
●「そんな失礼なことしません!」
――本日は、eBigComic4に掲載中の高橋留美子先生の『めぞん一刻』について、当時の担当編集者、鈴木総一郎さんにお伺いします。制作当時の裏話などをお聞かせいただければと思っています。それではよろしくお願いします。
鈴木 はい。でも『めぞん一刻』の連載を担当していたのはもう30年以上も前ですので、どこまで覚えているかわかりませんが、高橋先生は我々の「宝」ですから(笑)、できるだけ、きちんと答えようと思います。よろしくお願いします。
――では、まず『めぞん一刻』が「ビッグコミックスピリッツ」(以下「スピリッツ」)に連載されることになった経緯などをお聞かせいただけますか?
鈴木
私は3代目の担当編集なのですが、連載が始まった頃から反響が大きくて、2代目から引き継いだ時には、もう人気作品になっていました。
担当になる前から個人的にも好きな作品だったので、がんばろうと思っていましたが、比較的早い時期にトップを取っていましたので、むしろトップから落とさないようにすることの方が、編集者としては気を遣いました。
――そんなに反響が大きかったのですか?
鈴木 高橋留美子先生は、当時『うる星やつら』を「週刊少年サンデー」(以下「サンデー」)で1年か2年ぐらい不定期ですが連載されていて、すでに人気でした。その気鋭の作家が、初めて青年誌である「スピリッツ」に執筆する、しかも、それが若い女性作家だということで大変話題になりました。
――高橋留美子先生の掲載を決めたのはその時の編集長だったのですか?
鈴木 はい。「スピリッツ」は「ビッグコミック」系の青年誌ですので、当初、作家陣は「ビッグコミック」系の作家プラス新人作家という構成でした。創刊の時に集まったスタッフが「これはどうだろう」と作品を持ち寄ったのですが、その中に「サンデー」から移籍してきた初代の担当だった人が、高橋留美子先生を引っ張ってきたという形ですね。
――鈴木さんは「スピリッツ」の前は、どちらの編集部にいらっしゃったのですか?
鈴木 「ビッグコミックオリジナル」の編集部にいたのですが、「スピリッツ」が創刊される時に、ビッグの編集部に「スピリッツ」の創刊準備室が出来まして、「スピリッツ」の創刊とともに移籍しました。
――どの時期から『めぞん一刻』に関わられたのですか?
鈴木 単行本第1巻の8話か9話あたりから、単行本の11巻目あたりまでだったと思います。まあ、前半、中盤の「おいしいところ」を担当させてもらいました(笑)。
――ちなみに、高橋留美子先生以外には、どのような先生方を担当されていましたか?
鈴木 長くやっていますので、いろんな方を担当させていただきました。当時は青年誌に女性作家が描くというのが珍しかった時代ですが、「スピリッツ」には高橋留美子先生以降、けっこう、女性作家が多くなりまして、柴門ふみ先生や石坂啓先生も担当させていただきました。大御所の水島新司先生、新人だったいわしげ孝先生、『軽井沢シンドローム』のたがみよしひさ先生、細野不二彦先生の『ギャラリーフェイク』なども担当しました。

――あの、これは大変失礼な質問かもしれないのですが、鈴木さんは『めぞん一刻』の「惣一郎さん」のモデルというのは……?
鈴木 これは偶然です(笑)。もちろん、光栄ではあるのですが、私が担当になる前から、すでに名前が決まっていましたので。
――偶然ですか!
鈴木 はい。高橋先生も「担当の方を犬の名前にするなんて、そんな失礼なことはしません」とおっしゃっていました(笑)。
●「『めぞん一刻』の冒頭は漫画の教科書ですよ」

――『めぞん一刻』はキャラクターの一人ひとりがとても魅力的で、彼らの織りなす人間模様も見事ですね。この作品を始められた時、高橋先生はまだ、20代前半だったとは驚きです。
鈴木 そうですね。高橋先生は大学在学中に「サンデー」で『うる星やつら』を始められ、それから1年ぐらい経って、大学を卒業されたのを期に、「スピリッツ」で『めぞん一刻』を始められたんです。
――すごいですね。当時から高橋先生は異彩を放っていましたか?
鈴木 それはもう、ただ者ではないですよね。
――『うる星やつら』とはずいぶんイメージが違いますが、驚かれたファンも多いでしょうね。
鈴木 舞台が青年誌ということで、『うる星やつら』のSF+ギャグというジャンルから、全くイメージの違うラブコメという新しいジャンルに挑戦されたんですが、それでも『めぞん一刻』の最初の頃には、まだギャグっぽい臭いがありますが。
――確かに、『めぞん一刻』の第一話は冒頭から、畳み掛けるようなギャグシーンではじまりますね。数ページで、五代くんを中心に主要キャラクターが次々に登場して、3ページぐらいで、一気にキャラクターを見事に立てていくところは圧巻ですね。
鈴木 この1話目は、漫画を描く人の「教科書」ですよ。
●「どうして男の気持ちがわかるんだろうか」
――キャラクターたちの心理描写、特に男性作家が描くような理想化された女性像ではなく、女性ならではの心理描写が素晴らしいですね。たとえば、朱美さんや一ノ瀬さんが、管理人さんに核心をついた事を言ったりするところとか。
鈴木 朱美さん、いいですよね。響子さんは、何を考えているのか、よくわからないところがあるんです。五代をかき回したり、スネたりする。
――確かに。機嫌が悪くなったり。
鈴木 女性の気持ちや本音、決して可愛いだけじゃない生身の女の人の思いなどを、女性作家らしい細やかな心理描写で描かれる一方で、高橋先生は「どうして男性の心理がこんなにわかるんだろう」とも思います。たまに下ネタというか、男の卑猥なところをえぐるようなことを描かれたり。「なんでわかるの?」と(笑)。
――男性の意見を代表して、編集の方がアドバイスしたりすることはありましたか?
鈴木 打ち合わせでは、たとえば「次は温泉に行かせませんか」みたいな、提案はしていましたが、特に男性の気持ちを解説したり、ということは、あまりなかったですね。男性の心理をよくお分かりになっていて、ネームでも全然違和感がなかったです。五代と友人の坂本の会話なんか、まったく自然ですよね。
――五代くんと響子さんの関係をギクシャクさせる、一つの出来事が解決すると、次は違うキャラクターが出てきて、またトラブルを巻き起こす、といった形で、見事なストーリーテリングで、読者を全く飽きさせませんね。
鈴木 飽きさせないように物語を作ろう、ということではなく、キャラクターが勝手に動いてくれているような感じでしたので、打ち合わせでは「このキャラクターはこういうシチュエーションだったら、こう動くよね」と、キャラクターたちを誘導するような形で話を詰めてました。すべてのキャラがちゃんと立っているので、彼らが物語を作ってくれたようなものですね。
●大炎上した「あの事件」!?
――7年間の連載の中で、五代が浪人生から大学生になり、卒業して就職、結婚という、人生の中でも重要な時期、青春時代を描き切った感があるのですが、高橋先生はそのあたりの構想は当初からお持ちだったのでしょうか。
鈴木 そこまでは考えておられなかったと思います。主人公については、当時「スピリッツ」は20歳前後の読者を想定していましたので、素直に考えると大学生だろう、そして、恋愛の相手は、やや年上のアパートの管理人さん。ということで、この二人で、どうお話を作っていくか、ということからスタートして、ドラマがどんどん盛り上がってエスカレートしていく中で、最後をきちんと終わらせるためには、やはり、卒業して、就職して、結婚してという、そういう形に必然的になっていったわけですが、全体を最初から考えて作ったというわけではないと思います。
――最初は『うる星やつら』のようなドタバタコメディ漫画になると予想した人もいたんじゃないしょうか。
鈴木 ただ、「スピリッツ」のような青年誌が、少年誌とどう違うかというと、恋愛という要素は少年誌にもありますが、青年誌の場合は、性行為は描かないにしても、少年誌に比べると、よりリアルな形で描いていくことになります。ですので、少年誌連載である『うる星やつら』のようなドタバタコメディにはできなかったと思いますね。

――なるほど。むしろ少年誌ではできないことを描くということですね。確かに『めぞん一刻』には五代くんが坂本と一緒に風俗店に行ったというようなくだりなどもあって、驚いた読者も多かったと思います。
鈴木 あれは……いろいろ言われているようですが、高橋先生ご自身は、五代くんと響子さんとの関係において、五代くんが未経験なのはダメだと考えておられたようです。
――それは、どういうことでしょうか?
鈴木 響子さんは未亡人なので、当然経験があるわけですが、五代くんに経験がなかったら、どうしても響子さんが主導する展開になってしまう。でも、先生はそれは違うとお考えだったようですね。五代が主導すべきだから、五代が未経験ではいけない。
――確かに、年下で頼りない五代くんが、そこも主導してもらったら、立つ瀬がなくなってしまうかも…。
鈴木 それで、いろいろありましたが、ああいう形で「匂わせる」程度の感じでお話を作ったわけですが……私が驚いたのは、その話の是非よりも、読者の反響がすごかったんですよ。
――どういう反響があったんですか?
鈴木 「なぜ響子さんがいるのに、五代をそんなところに行かせたのか!?」「最初の女性は響子さんじゃなきゃいけない!」というハガキやお手紙が、編集部にいっぱい来たんです。しかも、それはほとんどが男性読者からなんですよ。
――女性からではなく、男性から! それは意外ですね。
鈴木 昔と違って、今は男性が純潔を守る時代か、時代が逆転したんだな、と思って驚きました。まあ、それだけ、読者は二人に感情移入してくれていたわけですよね。
――今日ならば「大炎上」といった感じですが、こういった読者の反響も、先生には作品作りの参考にされるんですか?
鈴木 参考としては目を通されますが、それで影響されたり、右往左往したりすることはなかったですね。「何が面白いか」ということをちゃんとご自身の中にお持ちなので、
――『めぞん一刻』は女性のファンも多かったんでしょうね。
鈴木 はい。それに「スピリッツ」自体も女性読者が多かったんですよ。どちらかというと、彼女と一緒に読む雑誌というイメージがあって、こちらも密かにそう思って、わざとそういう作り方をしていた部分もあります。女の人が読んでも、引かない、ちゃんとしたものを作ろうという意識はありました。
●高橋先生は「努力する天才」なんです!
――高橋先生はある程度、文字でプロットや粗筋のようなものを作られてからネームに入られるのですか? それとも、いきなりネームから?
鈴木 そうですね。第一稿はネームですね。
――ネームの段階で、編集から「ちょっと違うんじゃないか」という形で「ボツ」になったりすることはないのですか?
鈴木
「ここはこうした方がいいんじゃないですか」という、微調整のようなことはありましたが、完全に描き直しというのは全くなかったですね。
打ち合わせをすれば、だいたい「こうなるだろうな」という仕上がりが見えてきますし、どこかに不安が残るようなら、「もっと話しましょうか」となりますし。
――打ち合わせで、だいたい決まるわけですね。
鈴木 そうですね。でも、普通は漫画家さんと、こうした打ち合わせすると、「100」打ち合わせたとしたら、「60」で上がってくれば「まあまあ合格」で、「80」だったら「やった!」という感じですが、高橋先生の場合はそれが「150」とか「200」で返ってくるんですよ。
――予想を常に超えてくるわけですね。
鈴木 はい。私が言うのもなんですが「天才」、それも、矛盾する言葉ですが「努力する天才」なんです。天才なのにちゃんと努力している。「すごい方」としか言いようがないんです。でも、だからといって作品がスラスラと出てくる、というものではなくて、やっぱり、悩まれて、苦しまれて、苦労されて、出て来るものなんですよ。
――高橋先生を担当されたばかりの時の印象と、長くお付き合いされてからの印象は変わりましたか?
鈴木 高橋先生は最初から、お仕事に対して、ちゃんとしてらっしゃいましたね。プロフェッショナルです。原稿が早くて、面白い。それはずっと変わりません。
――プロ意識がすごいんですね
鈴木 やはりすごいと思いますね。ある時、打ち合わせの少し前に地震があったんですよ。けっこう揺れたんです。高橋先生に「地震すごかったですね」という話をしましたら、先生が「地震はいやですね」と言われて。続いて「怖かった」みたいなことをおっしゃられると思ったら、「だって、印刷所が止まったら、私が描いた漫画が読者に届かないじゃないですか」って(笑)。
――ええっ!?
鈴木 これがプロだ、と再確認しましたが、そういう印象も最初からずっと変わっていないです。
●『うる星やつら』と『めぞん一刻』、驚異の同時週刊連載!
――当時、『うる星やつら』と『めぞん一刻』、二つの作品を同時に週刊連載されていたわけですよね。
鈴木 はい。私自身は高橋先生の担当をさせていただいて、楽しいことばかりだったんですが、先生には申し訳ないことをしたなあ、というのがありまして……。
――申し訳ないとは……?
鈴木 「スピリッツ」は最初の半年は「月刊」だったんですね。それから「隔週刊」になり、2年ぐらい経ってから「週刊」になるんです。
――それだけ「スピリッツ」の人気が出てきたと。
鈴木 ただ、「隔週」だったのが「週刊」になるということは、作家さんにとっては大変なことなんですよ。今までの2倍を描かなきゃいけなくなるわけですから。
――なるほど。サンデーもあわせれば、1週間7日の間に締め切りが2回も来ることになるわけですね。
鈴木
週刊での『うる星やつら』に加えて、隔週で『めぞん一刻』を連載するだけでも、けっこうカツカツだったのですが、その隔週だった連載を、「週刊にしてくれませんか」とお願いに行ったわけですから。
高橋先生も最初は「えーっ!」という感じだったんですが、そこはプロなので、最終的に「やります」って言ってくださったんです。
――すごい。プロですね。
鈴木 その後、先生は『めぞん一刻』の完結まで4年ぐらいの間、一度の休載もなく週刊連載を毎週2本やっていかれたわけです。うら若い女の子なのに、プライベートのお休みは正月しかなく、あとは毎日毎日原稿に向かう状況に追い込んだわけですから、やはりそこは、大変申し訳なかったなあ、と思っているんです。それだけでも頭が下がります。
――高橋先生は当時、ネームにはどれくらいの時間をかけられていたのですか?
鈴木 私が担当していた時は一晩でしたね。そうでないと回らないので。
――アシスタントさんは大勢いらっしゃったんですか?
鈴木 最初は2人でしたが、週刊になってからは4~5人くらいだったでしょうか。
――作品ごとに班を分けてらっしゃったんでしょうか。
鈴木 分けていなかったです。高橋先生のところはアシスタントさんも先生に似て優秀だったので、助けられました。
――「サンデー」と「スピリッツ」、どちらも小学館の雑誌ですが、締め切りのせめぎあいのようなことはあったんですか?
鈴木
それはなかったです。高橋先生はちゃんと締め切りを守られるんです。スケジュールを決めて、その通りにやってくださる。たまに風邪を引かれたりして、多少ずれ込むことはあったとしても、それでも、ちゃんと締め切りは守るんです。
「早くて面白い」作家というのは、編集者としては最高の作家さんですね。中には「遅くてつまらない」という方もいらっしゃいますので。
――お仕事しやすい作家さんなんでしょうね。ずっと担当でいたいというような。
鈴木 そうなんですよ。ただ、高橋先生はそれだけプロに徹していらっしゃるので、こちらも頑張ってプロに徹しなければいけないんです。だからこそ、編集者も始終作品のことを考えていなければいけないのですが、その分、充実した仕事ができる作家さんだと思います。
●一刻館は『擬似家族』である!?
――『めぞん一刻』の中で、鈴木さんが好きなキャラクターは誰ですか?
鈴木 基本的に全部好きです。全てのキャラクターが魅力的なんですよ。朱美さんも、八神も、こずえちゃんも好きです。四谷さんもいい。すごいバイプレーヤーですし。あと五代のおばあちゃんも秀逸ですね。
――本当に活き活きとした、憎めないキャラクターばかりですよね。悪い人は一人も出て来ない。
鈴木 そう。悪人は出てこないんです。だから、最終話までに、それぞれみんな、きちんと幸せになっていくんです。でも、悪人を出させずに作品を作るのは、それはそれで大変なんですが。

――ライバルである、三鷹さんも「いい人」ですね。
鈴木 五代くんは、お金も力もない頼りない男なのに、やさしさと一途な想いだけを武器にして、三鷹さんに勝つわけですよね。それは当時の世相というものも関係するでしょうが、今でもちゃんと成立することじゃないかと思います。今だったら「三鷹の方がいい」という女性も結構いるかもしれませんが(笑)。
――きっといるでしょうね。イケメンでお金持ちですし。
鈴木 あと、『めぞん一刻』について、よく言われるのが、「擬似家族」ということですね。「一刻館」自体が一つの家で、おじさんおばさんのような役割の四谷さんや一ノ瀬さんがいて……そういった家族の体験もできるという。
――言われてみれば、確かに大家族的ですね。
鈴木 当時、大家族制度が崩壊しつつありましたが、一刻館の中では、いろんな人に囲まれながら、ちゃんと安らげる場所がある。『めぞん一刻』はそういうことも味わえる世界ではないかと思います。だから、最後はああいうシーンでエンディングを迎えたというわけでしょう。
――アットホームさも、一刻館の魅力ですね。五代くんの置かれている、お金がなかったり、仕事がなかったりといった感覚は、むしろ、今の若者により響くかもしれませんね。
鈴木
そうですね。今の状況の方がシビアかもしれませんけどね。当時は、幻想かもしれないが、五代くんの恋愛だけには夢があったし、金はないけど、今より未来はあったという気がするんですよ。当時は、五代くんにしても、まじめに働けば、ちゃんと一家を養っていけるというのがあった気がしますから、
ただ、今だと恋に一途な男は、ちょっと間違うと「ストーカー」だとか、変な人だとかと言われてしまいかねないですが(笑)。
――『めぞん一刻』の中で、特に好きな話はありますか?
鈴木 いや、すべての回にそれぞれの面白さがあり、どの回も好きですが、さっきお話ししたハードなスケジュールのなかで、一度だけ、さらに、増刊号にも描いていただいたことがありました。単行本の6巻に収録されている「一刻島ナンパ始末記」という話がそれで、本筋には関係のないばかばかしい話なのですが、とても楽しい話で、個人的には好きです。
――それでは、最後に、このインタビューを読んで『めぞん一刻』を読んでみたいと思った人や、これから読もうと思っている人もいらっしゃるかと思います。そういった新しい読者へのメッセージなどはありますでしょうか。
鈴木 絶対に期待を裏切らない、間違いなく面白い作品ですので、ぜひ読んで欲しい、というのが一番ですね。

――おそらく、100年後にも読まれ続けている作品ではないでしょうか。
鈴木 そうなればいいなと思います。
――どうもありがとうございました。

